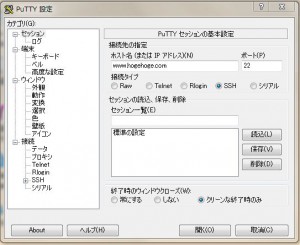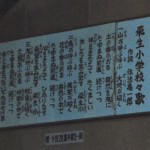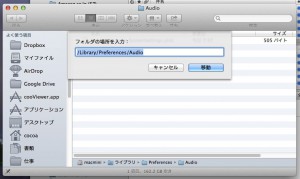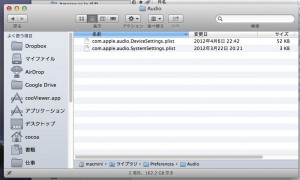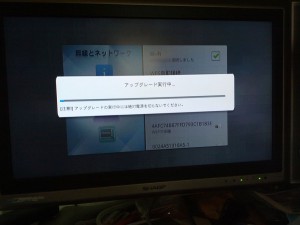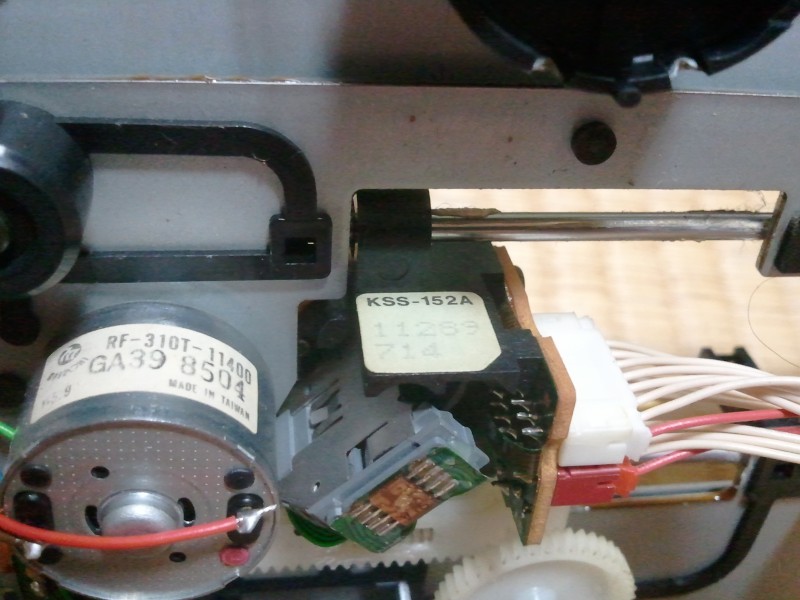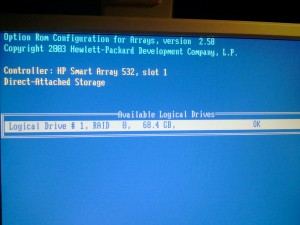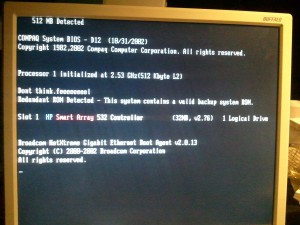Olasonic TW-S5買ってみた。
USBの電源供給だけで10Wの出力を実現するというスピーカー。
アマゾンで7,999円

さて、お楽しみ。
Macminiに繋いである8ポートのセルフパワーUSBハブに繋いだ。
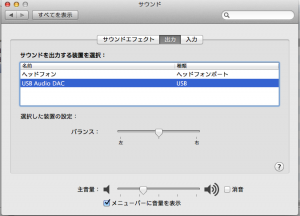
Macからはこのように認識する。
最初から音量がMAXになるので音量下げてから再生しよう。
かなりデカイ音が出る。
音は正直驚いた。
凄い。こんなに鳴るのか。と。
サイズからは想像できない落ち着きある音。
USBバスパワーであることなんて嘘だと思ってしまう音量。
普段は1998年製のSONY SRS-Z500PCを使って居るが軽く抜きさる音質。
ビリージョエルを聞くと”Uptown Girl”のコーラスなど鳥肌もの。
空気感にほんのちょっとぎこちないところがあるが、
おそらくはエージングで解決すると思う。
くるりの「ワールズエンド・スーパーノヴァ」のビートもバッチリ。
n-tranceのStay’n Aliveも気持ちよく聴ける。
凄いモノが出た。
※注意点としてIntel P55チップセット(Core i5/i7の場合がある)…P55関連USBエラー説明と
AtomCPUのパソコンとは相性がよろしくないそうです。購入前に自分のパソコンの確認を。
これはスピーカーの品質では無く、他の機器でも問題の出ているUSBです。